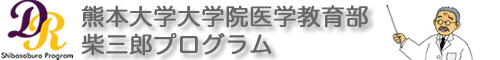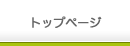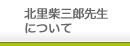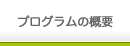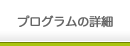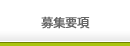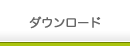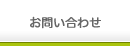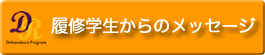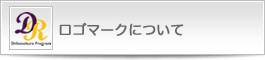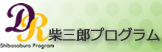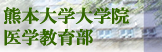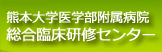Archive for the ‘最新情報’ Category
平成26年度 柴三郎プログラム学生募集要項をUPしました
柴三郎プログラム公式HPのTOPページ上段のある「募集要項」のページに、平成26年度 柴三郎プログラム学生の募集要項を掲載致しました。出願期間および出願書類の提出先は、以下の通りです。よろしくお願い致します。
1.出願期間:平成26年2月27日(木)~平成26年3月5日(水)17時必着
2.出願手続:封筒の表面に、「医学教育部博士課程出願書類 在中」と朱書きをし、書留速達郵便にて下記まで郵送願います。
【出願書類送付先】
〒860-8555熊本市中央区黒髪2丁目40番1号
熊本大学学生支援部入試ユニット
※出願書類の一覧につきましては「募集要項」のページに詳細を掲載致しておりますので、ご確認ください。また、「卒後臨床研修宣誓書」の様式につきましては、当HPの「ダウンロード」ページにも宣誓書の様式を掲載致しておりますので、ご利用下さい。
平成26年度前期 プレ柴三郎プログラム学生の募集要項をUPしました
柴三郎プログラム公式HPのTOPページ上段のある「募集要項」のページに、平成26年度前期 プレ柴三郎プログラム(先取履修生)募集要項を掲載致しました。出願期間はおよび出願書類は以下の通りです。よろしくお願い致します。
1.出願期間:平成26年2月3日(月)~平成26年2月7日(金)16時必着
2.出願手続:熊本大学生命科学系事務ユニット医学事務チーム教務担当
3.出願書類:①先取履修願(所定様式)、②履歴書(所定様式)
※出願書類の様式は、ダウンロードのページにて掲載致しております。
第5回柴三郎プログラムセミナーが無事終了しました
今回は、岡山大学からアメリカのロックフェラー大学大学院に進学され、現在はイェール大学にてポスドクとして研究を継続しておられます、佐伯恭範(さえき やすのり)先生をお招きし、お話し頂きました。
医師国家試験に合格し学部を卒業したのち、卒後臨床研修に進まないで、海外の大学院に進学し、研究を続けられているとのこと。学部時代には昼休みや放課後を利用して研究を6年生の夏まで続け、その後に医師国家試験対策を行ったとのことで、勉強と研究の両立を図られたようです。
先生のお言葉の中で、「医師国家試験をパスしていれば、医者にはいつでも戻れる。研究を継続することの方が面白いので、今は出来るだけ研究を続けたい。」とおっしゃられていたのが、印象に残りました。
佐伯先生のような進路もある、ということを今回初めて知った学生にとっては、目からウロコな話題ではなかったでしょうか。基礎医学研究を続けるにあたっての進路の選択肢は、いくつかあるのかも知れませんね。本学医学生の皆さんの今後の進路選択の一助となれれば幸いです。
 |
 |
第5回柴三郎プログラムセミナーを開催致します
開催日時:平成26年1月21日(火)17時~18時30分
開催場所:医学教育図書棟3F 第1講義室(いつもと違うので、お間違いなく!)
参加対象者:本学医学科学生、大学院生、教員
内容:今回のセミナーでは、新進気鋭の若手研究医の佐伯先生をお招きし、お話しをしていただきます。佐伯先生は、岡山大学医学部で学部学生の時より基礎研究室で研究を行っていました。学部学生の時に、すでに筆頭著者で論文を書かれています。卒業後、卒後臨床研修に進まず、ロックフェラー大学の大学院に進学されました。大学院修了後、現在Yale大学でポスドクをされており、CellやNature Neuroscienceに筆頭著者として論文を書かれています。
医学部生の卒後進路として、海外で挑戦する道もあるんだということ、また海外での苦労話や悩みなど、ざっくばらんに話をしていただきます。32歳と若く、皆様のお兄さんのような先生なので、気楽に聴講して、何でも質問して下さい。
「第5回柴三郎プログラムセミナー」のチラシはこちら!!
http://www.shibasaburo-kumamoto.jp/wp-content/uploads/H25-5-seminner.pdf
平成25年度「プレ柴三郎研究発表会」応募要項をUPしました
平成25年度「プレ柴三郎研究発表会」を以下の日程において、開催致します。
応募要項および抄録様式につきましては、当HPの募集要項ページおよびダウンロードページにて掲載中です。よろしくお願い致します。
開催日時:平成26年2月28日(金)14時半~17時50分
開催場所:熊本大学本荘キャンパス臨床医学教育センター1F 奥窪記念ホール
※エントリーは柴三郎プログラム事務局宛てに、所属分野・学年・氏名(ふりがな)、携帯番号を明記のうえ、メールにてお送りください。(エントリー〆切:1月31日)
エントリー送付先:info@shibasaburo-kumamoto.jp
※抄録につきましては、Eメールにて後日送付願います。(抄録〆切:2月14日)
※プレゼン用pptファイルも事前に動作確認致したいので、2月21日(金)までに、ご提出下さい。よろしくお願い致します。
スーパーサイエンス指定校の高校生が来校しました
スーパーサイエンス指定校(SSH)に指定されている熊本第二高校ならびに熊本北高校の高校生11名が、医学部を訪ねてくれました。
午前中は、糖代謝、糖尿病について講義をし、コーラや0キロカロリーコーラを飲んだら血糖値がどうなるか演習をしました。
午後からは、高校生の皆さんに糖尿病モデルマウスの血糖値を測定してもらったり、マウスの解剖をしていただいたりしました。また、iPS細胞を観察してもらいました。
全員、目を輝かせながら実習に取り組まれていました。「柴三郎Jr.の発掘プログラム」にも興味を持っていただいたようです。来校いただいた皆さんが、今後医学研究に取り組まれることを期待しています。
 |
 |
第4回柴三郎プログラムセミナーが無事終了しました
今回は京都大学より、斎藤通紀(さいとう みちのり)先生をお招きして、「基礎医学研究の魅力:生命科学は、わからないこと、出来ないことであふれている」と題して、ご講演頂きました。精子や卵子などの生殖細胞は唯一、滅びない細胞という事に魅力を感じたから、現在のような研究を始めることとなったそうです。
発見と発表の積み重ねが医学・生命科学の教科書となり、創薬や新しい医療技術開発に繋がり、それらが世代を超えて受け継がれるということに魅力を感じ、基礎医学研究を続けられているとのこと。
今後はマウス実験だけでなく、ゲノム配列がヒトと近似している霊長類であるカニクイザルを使って研究を続けていくとのことでした。今後の発表が楽しみです!
 |
 |
次回の「柴三郎プログラムセミナー」も詳細が決定致しましたら、追ってお知らせ致しますので、皆さんお楽しみに!!
熊本大学・愛媛大学・岡山大学3大学合同シンポジウムが無事終了しました
平成25年10月17日(木)14時より熊本大学臨床医学教育研究センター1F奥窪記念ホールに於いて、基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成プログラム・組織的な大学院教育改革推進プログラムに採択された西日本の3大学による合同シンポジウムを開催し、無事閉幕致しました。
 |
 |
 |
 |
本学学生も「楽しかった!良い刺激になった。」というご意見をたくさん頂きました。参加なさった全ての学生にとっても良いシンポジウムになったようです。
 |
 |
 |
 |
今後も引き続き、このような発表および交流の場が設けられたら良いと思いました。ご参加の皆様方、本当にありがとうございました。
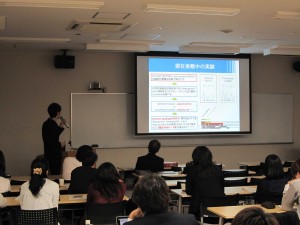 |
 |
 |
 |
※学生によるパネルディスカッションの要約はこちら!
http://www.shibasaburo-kumamoto.jp/wp-content/uploads/panel-discussion1.docx
第4回柴三郎プログラムセミナーを開催致します
開催日時:平成25年10月25日(金)17時~18時30分
開催場所:医学教育図書棟4F 第3講義室(いつもと違うので、お間違いなく!)
参加対象者:本学医学科学生、大学院生、教員
内容:今回のセミナーでは、世界で初めてES細胞やiPS細胞からの精子や卵子を作成することに成功した斎藤通紀(さいとう みちのり)先生にお話しをしていただきます。斎藤先生は、今後、我が国の基礎研究をリードする若手研究者の一人と多方面から注目されており、文部科学大臣賞やゴールドメダル賞など多くの賞を受賞されています。京都大学医学部ご出身で、学部学生の時より基礎講座に出入りし、研究に没頭されておられました。4年生の時には留学もされ、学部学生時代に2本の論文を書かれておられます。
今回は、基礎医学研究者の第一人者でおられる斎藤先生に、基礎医学研究の魅力について熱く語っていただきます。医学生必見です!!
「第4回柴三郎プログラムセミナー」のチラシはこちら!!
http://www.shibasaburo-kumamoto.jp/wp-content/uploads/4-seminner.jpg
柴三郎プログラム便りvol.1が完成しました
熊本大学基金内に創設されました「柴三郎プログラム基金」へご寄付を頂きました方々に、本プログラムの活動内容や近況報告、寄付金の収支について年2回(半年に一度)ずつ標記便りを発送することといたしました。本基金により奨学金支給が可能となった学生のインタビューや、今後の活動予定などが掲載されております。寄付を募って頂きました皆様への心ばかりの御礼ですが、本プログラムの活動の様子が垣間見ることが出来れば、幸いに存じます。
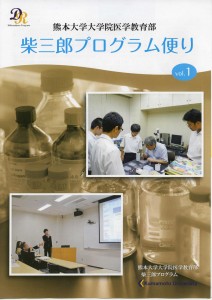 |
« Older Entries Newer Entries »